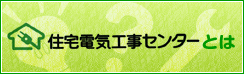関東地区電気エネルギーを考える委員会主催の講演会が開催されました。
| 講 師: | 株式会社e-Mobility Power
充電設備部
遠藤 寛明 様 |
| テーマ: | 「EV 充電インフラを巡る現状と今後の動向について」 |
| ねらい: |
2050年カーボンニュートラル実現に向けた「電化」「電動化」の動きは時代の潮流となって積極的に推進されており、今後も加速度的に進捗していくものと思われます。
このようにインフラとしての「電気」の重要性は一層増しており、私たち電気工事業への社会の期待も大きくなっております。この「電動化」の鍵を握るEV充電器の最新動向について把握し、身に付けた知識を地域へ周知啓発することで、時勢を鋭敏に捉え、カーボンニュートラル実現に貢献する業界を形成することを目的に、関東地区電気エネルギーを考える委員会主催により講演会を開催いたしました。
|
概 要:
(1) EVの優位性・環境影響
|
|
- 日本におけるCO2排出量の内、自動車は15.9%を占める。
- 自動車において、環境への影響を検討する際、次の3点が考慮される。
①走行のみ :走行時のCO2排出量
②+燃料精製:①に、エネルギー源から供給までのCO2排出量も含む
③+製造廃棄:②に、自動車の製造から廃棄までのCO2排出量も含む
- 上記環境影響(CO2排出量)について、EVの優位性は次のとおり
(2020年欧州分析)
①走行のみ :EVはガソリン車に比べ、約40分の1の排出量(ほぼゼロ)
②+燃料精製:EVはガソリン車に比べ、約4分の1の排出量
③+製造廃棄:EVはガソリン車に比べ、約2分の1の排出量
|
(2) CHAdeMO規格をはじめとした各種充電規格
|
|
- 充電規格(充電器口形状)については、日本のCHAdeMO規格をはじめ、各国様々な規格がある。
- 日本国内においては、普通充電器は「Type1(SAE J1772)」、急速充電器は「AA(CHAdeMO)」が採用されている。テスラ社製EVに向けては、テスラ社の規格も設置されている。
- 近年米国で台頭するテスラ社については、まだ国際標準規格ではない。
- しかし米国では順次置き換えが進んでおり、すでに半数以上がテスラ社の規格へ置き換わっている。
|
(3) V2H/V2Gについて
|
|
- EVから家庭に給電するV2Hには、系統連系型/非系統連系型の2種類があり、系統連系型の場合は、EVから家庭への給電、電力会社からの送電、並びにPVによる創電を含めた3系統の同時利用が可能。
- EVから電力系統へ電力供給するV2Gは、多数のEVを遠隔制御することで、電力系統の調整力として運用が可能。
- いずれも、EVを災害時の非常用電源、蓄電池としての活用することが可能。
|
(4) e-Mobility Powerと充電インフラの概要
|
|
- 「いつでも、どこでも、誰もがリーズナブルに充電できるサービスの提供」を掲げる株式会社e-Mobility Powerは、パブリック充電サービス領域を軸に、他社が投資するプライベート領域の充電器の設置・運用・保守から、家庭の車庫へのEVコンセント設置までワンストップで提供している。
- e-Mobility Powerの展開する公共充電ネットワークにより、1枚のカードで各地に点在する、様々な企業・自治体の設置した充電器を利用可能。
|
(5) 日本の充電インフラの現状と課題
|
|
- 政府のグリーン成長戦略以降、充電インフラの整備は増加基調にあるが、「初期に導入され、インフラ構築の礎となった充電器の老朽化」、「大都市に近い高速道路にて、土日祝に充電渋滞状態が発生」、「山間部や、スペースのない都心部等における急速充電器の空白地域残存」等様々な課題も抱えている。
|
(6) 課題解決~充電器の口数増加と出力向上への取組み~
|
|
- 老朽化、充電渋滞の解消のため、充電器の複数口化・高出力化を推進。
- 2024年度には、複数車両を同時充電できる高出力充電器を中心に高速道路SA・PAの119か所に約350口の新設・更新が計画されており、現在も推進中。
- 駐車場の少ない都心部で公道充電ステーションを運営し、空白地帯解消を狙う。
|
(7)課題解決~誰でも安心して利用できる取組み~
|
|
- 山間部の空白地帯解消、スペースがあり公共性の高い道の駅等ではバリアフリー
対応を意識したインフラ整備、公道上にEVトラックも利用可能な急速充電器を設置する等、様々な取組みをもって、EVの購入・普及の阻害要因となるインフラの不満足さを面的に整備・維持。
|
(8) 課題解決~機器開発と品質向上に向けた取組み~
|
|
- より高速の充電、操作しやすい次世代機の開発・設置。数を増やす取組みと並行して、不具合時の復旧を迅速なものとする諸施策による充電インフラ品質を向上。
- 市場投入前の車両を持ち込み、事前に様々な充電器互換性の確認が可能なセンターを開設することで、車両と充電器のマッチング不具合の予防。
|
(9) 施工時の留意
|
|
- 施工不良の例としては、充電時間や電流値の設定漏れ、その他は逆結線や切創、熱中症等。
- メンテナンススペースを考慮せず設置してしまう例も。
|
以 上